茶道 > 茶道の道具 > 蓋置 > 輪
輪蓋置
七種蓋置 印 輪 糸巻 駅鈴 夜学 笹蟹 三輪 墨台 つくね 硯屏 竹
輪蓋置(わのふたおき)とは、上下が吹貫きになった円筒形の蓋置です。
輪蓋置は、単に「吹貫」(ふきぬき)ともいいます。
輪蓋置は、元は台子皆具の一つで唐銅製の円筒形のもので、多くは精巧な地紋や透かしがあります。のちに陶磁製や竹製のものも造られます。
輪蓋置は、輪が中ほどで膨らんでいるものを「太鼓」(たいこ)、輪が中ほどで細くなったものを「千切」(ちぎり)といいます。また、一枚の木の葉を輪状に巻いた「一葉」(いちよう)、黒木を輪状に並べ括りを見せた「束柴」(たばねしば)などの意匠を施したものもあります。、
輪蓋置から派生したものに、四角、六角、八角、切子、亀甲、三日月など多様な変化があります。
『茶道筌蹄』に「輪 唐物写しなり」とあります。
 | |
 | |
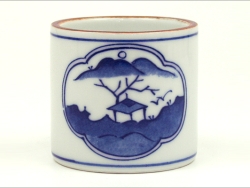 | |
 |
| 七種蓋置 | |
印 | |
輪 | |
糸巻 |
 | |
 | |
 | |
 |
| 駅鈴 | |
夜学 | |
笹蟹 | |
三輪 |
 | |
 | |
 | |
 |
| 墨台 | |
つくね | |
硯屏 | |
竹 |
 | |
 | |
 | |
 |
| 火舎 | |
五徳 | |
三葉 | |
一閑人 |
 | |
 | |
 | |
 |
| 栄螺 | |
三人形 | |
蟹 | |
七種 |
茶道をお気に入りに追加 |